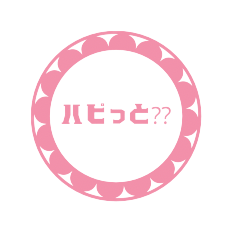侵害刺激とは?
「侵害刺激(しんがいしげき)」とは、体にとって有害な刺激のことを指します。たとえば、火に触れたときの熱さや、針で刺されたときの痛みなどがそうです。体はこうした刺激を感知し、「危険があるよ」と脳に伝えることで、私たちは素早く反応して体を守ることができます。
痛みを伝える神経の種類
痛みを脳に伝えるためには、感覚神経が働きます。神経にはいくつかの種類があり、それぞれに役割があります。
- Aβ(エーベータ)繊維
本来は「触った」「押された」などの軽い刺激を伝える神経です。太くて伝達が早く、痛みの抑制にも関係しています。 - Aδ(エーデルタ)繊維
「チクッ」とした鋭い痛みをすばやく伝える神経です。中くらいの速さで脳に信号を送ります。 - C繊維
「ズキズキ」「ジンジン」とした鈍い痛みをゆっくりと伝える神経です。最も細くて伝達が遅いのが特徴です。
痛みの抑制法
痛みを感じたとき、思わずその部分を「さする」ことがありますよね。実はこれ、ちゃんとした理由があるのです。
たとえば、足をぶつけて痛いと感じたとき、C繊維が「痛い!」という信号をゆっくり脳に送っています。そこにAβ繊維が「さすられている」という情報を素早く送ると、脳は「さすられている感覚」を先に受け取り、痛みの信号が一時的にブロックされることがあります。
これは「ゲートコントロール理論」と呼ばれる考え方で、太くて速い神経が、細くて遅い神経の信号を抑えるような仕組みです。簡単に言えば、「速い神経が先に脳に信号を届けることで、痛みが感じにくくなる」ということです。
まとめ
痛みは、体の危険を知らせる大切な信号です。しかし、その感じ方には神経の種類や太さ、伝わるスピードが関係しています。ぶつけたあとに思わずさするのは、自然に痛みを抑える工夫。身近な行動にも、ちゃんとした科学の裏づけがあるんですね。