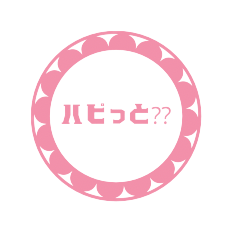私たちは「ストレスで食べ過ぎてしまう」「寝不足の翌日はつい甘いものが欲しくなる」そんな経験をしたことがあるのではないでしょうか。実はこの現象には、自律神経とホルモンの密接な関係が隠れています。
■ ストレスと交感神経が食欲を刺激するしくみ
ストレスを感じると、体は“戦うか逃げるか”の反応を示します。これは交感神経が活発になることで、心拍数や血圧が上がり、エネルギーを使いやすい状態にするためです。短期的には食欲を抑えることもありますが、問題は「慢性的なストレス状態」です。
過剰な交感神経の活動が続くと、体はエネルギー不足と勘違いし、「食べて補わなければ」と脳が指令を出します。特に糖質や脂質など、高カロリーなものを求めやすくなります。これはストレスホルモンであるコルチゾールが関係しており、血糖を上げる作用と同時に、食欲を増進させる働きを持っているのです。
■ 睡眠不足が食欲ホルモンを乱す
一方で、睡眠不足も食欲を乱す大きな要因です。睡眠が足りないと、食欲を抑える「レプチン」が減り、逆に食欲を高める「グレリン」が増えます。その結果、実際には必要のない量の食事を欲してしまうのです。
さらに、睡眠不足は脳の報酬系にも影響します。甘い物や脂っこい物を食べたときの「快感」が強く感じられるため、つい手が伸びてしまうのです。これは単なる意志の弱さではなく、脳の生理的な反応によるものといえます。
■ まとめ:整えるべきは「自律神経と睡眠」
ストレスも睡眠不足も、根本には自律神経の乱れがあります。交感神経が優位な時間が長くなれば、食欲コントロールは難しくなります。まずは「食べ過ぎを防ぐ」よりも、「休む時間を確保する」「深呼吸や軽い運動でリラックスする」ことを意識してみましょう。
食欲は心と体のバランスのバロメーター。無理に抑えるのではなく、整えることが何よりの近道です。