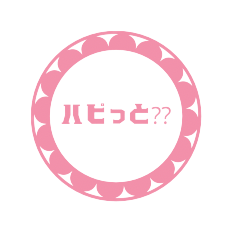「亜鉛は体に良い」と聞いたことがあっても、その理由を詳しく知っている人は少ないかもしれません。実は、亜鉛は血糖値をコントロールするホルモン“インスリン”と深い関係があります。ここでは、インスリンの基本的な働きと、亜鉛がそれをどう支えているのかを見ていきましょう。
インスリンとは?
インスリンは、すい臓のβ細胞から分泌されるホルモンで、血糖値を下げる唯一のホルモンです。私たちが食事をすると、血液中の糖(ブドウ糖)が増えます。するとインスリンが分泌され、糖を筋肉や肝臓、脂肪細胞に取り込み、エネルギーとして使ったり蓄えたりします。
インスリンが適切に働かないと、血糖が細胞に取り込まれず血液中に残ってしまい、いわゆる「高血糖」の状態になります。これが慢性的に続くと糖尿病へとつながります。
インスリンと亜鉛、糖尿病との関係
亜鉛は、インスリンの「構造を安定させる」ために欠かせないミネラルです。インスリンは体内で「亜鉛イオンと結合」することで、初めて正しい形に折りたたまれ、すい臓の中に安定して貯蔵されることができます。
さらに、インスリンを分泌するときにも亜鉛が重要な役割を果たします。亜鉛が不足すると、インスリンの合成や分泌がうまくいかなくなり、血糖コントロールが乱れやすくなるのです。研究では、糖尿病の人の多くに亜鉛不足が見られるという報告もあります。
また、亜鉛はインスリンの働きを助けるだけでなく、細胞の抗酸化作用や炎症の抑制にも関与しており、糖尿病による合併症の予防にも役立つと考えられています。
まとめ
インスリンが血糖値を調整する“主役”だとすれば、亜鉛はその“名脇役”です。亜鉛が不足するとインスリンが安定せず、糖代謝がうまく回らなくなる可能性があります。日常の食事では、牡蠣・牛肉・卵・ナッツ・チーズなどに多く含まれています。
糖尿病の予防や血糖コントロールを考えるなら、食事の中で「亜鉛を意識すること」がとても大切です。小さな栄養素でも、体の働きを支える大きな力を持っているのです。