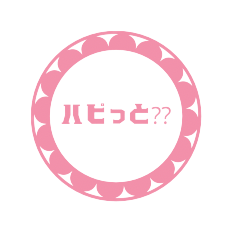私たちの体の中心を支える「脊柱(せきちゅう)」――つまり背骨は、ただの骨の連なりではありません。実はこの背骨、私たち人類がどのように進化してきたか、そして今どう生きているかを物語る重要なパーツなのです。
もともと地球上の生物は水中生活からスタートしました。魚類にはっきりとした脊柱が現れ、やがて陸上に進出した両生類や爬虫類へと進化。その過程で、移動手段も泳ぐことから這う、歩く、走る、跳ぶと多様になり、それに合わせて脊柱の形や役割も変化しました。例えば四足歩行の動物では、脊柱は体を水平に保ち、走るときのバネのような役割をします。
では、二足歩行になった人間はどうでしょう?人類が直立歩行を始めたことで、脊柱はS字カーブを描くようになりました。この形は、頭を支え、重力の衝撃を和らげるのに適しています。立って歩くにはまさに理想の構造だったのです。
ところが、現代人の生活スタイルは大きく変わりました。デスクワークやスマホ操作など、「座る」「前かがみになる」時間が圧倒的に長くなっています。本来S字を描くべき脊柱は、長時間の悪い姿勢によってまっすぐになったり、逆に不自然なカーブを描いたりして、肩こりや腰痛、猫背などの原因になっています。
つまり、私たちは進化の結果として手に入れた脊柱を、現代の生活でうまく活かしきれていないのです。だからこそ、時折立ち上がり、背筋を伸ばすことが大切なのです。
まとめ:
背骨は、私たちがどんな進化をしてきたのか、そして今どう生きているかを静かに語っています。便利さと引き換えに体に負担をかけている現代。未来の健康のためにも、自分の「背骨の声」に耳を傾けてみましょう。